

2025 年 1 月 25 日(土)に2024年度先天代謝異常症患者会フォーラムがWEB 配信で開催されましたのでご報告いたします。
1.開会のあいさつ「当学会の取り組みについて」
日本先天代謝異常学会理事長 中村 公俊 先生(熊本大学小児科)
中村理事長より、日本先天代謝異常学会の取り組みとして、
①国際プレゼンスの向上、②次世代リーダーの育成とジェンダーギャップの解消、③難病診療におけるレジストリー構築と基礎・臨床研究の推進、④関連学会・研究班・患者家族会との情報共有、⑤学会員と患者にとって持続可能な診療支援体制の構築、の5つの柱について説明がありました。
また、2025年9月に京都で開催予定の国際先天代謝異常学会学術集会の紹介があり、世界中の研究者・医療者・患者家族会が集う実りある学術集会とする意気込みを話されていました。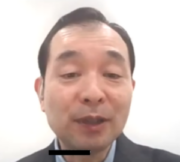
2.「先天代謝異常症における遺伝子診断の進め方とその意義」 岐阜大学 笹井 英雄 先生
笹井先生からは、遺伝の基礎から遺伝子診断とその後のフォローまで、わかりやすくお話がありました。
先天代謝異常症では、遺伝子検査の対象は幅広く、病気ごとの特性をよく理解したうえで検査を考えることが大切です。遺伝子検査を行うことで、病気の原因を明らかにし、より正確な診断や治療につなげることができます。また、家族全体での解析や血縁関係の中での検査も重要で、特にX連鎖性遺伝の場合は、結果の伝え方やご家族の気持ちに配慮した遺伝カウンセリングが欠かせません。さらに、未成年の発症前診断や保因者診断、出生前診断では、医学的な意味やご家族への影響を十分に考え、慎重に判断することが必要です。遺伝子検査は「患者さんにどのような医学的メリットがあるか」を常に考えながら行うことが大切であり、そのためにも遺伝カウンセリングが大きな役割を果たします。
最後に笹井先生は、遺伝子変異を特定し、長くフォローしていくことの意義について、「患者さんを中心に、保護者、医療者、研究者、そして患者会の皆さんが力を合わせて、お子さんたちの明るい未来を守っていくことにつながる」とお話されました。

3.「ライソゾーム病診療のパラダイムシフト」
医誠会国際総合病院 酒井 規夫 先生
続いて酒井先生からは、生命の誕生と人生、健康と疾病、ライソゾーム病とは何か、そして医療におけるキュアとケア、ライソゾーム病診療のパラダイムシフトについてお話がありました。
クラッベ病とファブリー病を例に、ライソゾーム病の多くは希少難病であり、自然歴や治療効果のエビデンスが得にくいこと、それでも患者・家族は病気と向き合い、主治医は診断と治療を続けなければならないこと、発症後の診断には時間がかかり確定診断までに進行してしまう例も多く、進行後は治療効果が限定的であることが課題です。近年では新生児マススクリーニングの導入により、発症前に診断できる疾患が増え、根本的治療法の研究も進んでいます。遺伝学の進歩により、ライソゾーム病はもはや「不治の病」ではなくなりつつあり、遺伝子治療など新たな治療法が次々と開発されています。
また、遺伝学的検査による発症前診断、家族歴のある場合の出生前・着床前診断も始まりつつあります。さらに、遺伝カウンセリングによる心理社会的支援の広がりも重要な変化です。
酒井先生は、「ライソゾーム病の診療はいままさにパラダイムシフトを迎えている」と結ばれました。課題は多いものの、確実に新しい時代へ進みつつあります。

続いて JaSMIn 事務局と小須賀先生から、先天代謝異常症患者登録制度(JaSMIn)の最新状況と研究成果について報告がありました。
JaSMInは患者登録事業の開始から今年で 12年目を迎え、患者様・ご家族とともに歩んできました。新規登録の推進、維持・更新、情報提供や研究への活用などを通じて、全国の皆様とつながり続けています。今後も関係患者会と協力しながら、新規登録の呼びかけやイベント案内などを進め、長期運用に伴う課題の解決、登録情報の関連研究への活用推進、患者さんへの情報還元を一層進めてまいります。
小須賀先生からは、JaSMInを活用した研究の紹介がありました。2024年度は新たに2件の研究が実施されました。1つ目は「先天代謝異常症の子をもつ主養育者のメンタルヘルスとQOL調査」、2つ目は「ファブリー病患者のQOLと外気温変化における関連:縦断的観察研究」です。また、「先天代謝異常症の子をもつ主養育者のメンタルヘルスとQOL調査」を実施された小早川亜美さん(慈恵会医科大学)に代わり、研究内容を発表されました。研究では、病気の受容が進んでいても、QOL(生活の質)は低下している可能性が示唆され、養育者自身の生活背景や、サポート環境などを踏まえた多角的な支援必要性が指摘されました。


6.「先天代謝異常学会を終えて~患者会とともに歩む~」
国立成育医療研究センター 総合診療部 窪田 満 先生
窪田先生は、2024年11月7日(木)〜9日(土)の3日間、ステーションコンファレンス東京で開催された、第65回日本先天代謝異常学会学術集会ならびに第20回アジア先天代謝異常症シンポジウムの大会長を務められました。学術集会のテーマである「100万人に一人はゼロじゃない」は、希少疾患であっても「その一人」に向き合うことの大切さが込められています。学会では、診断のための臨床推論や遺伝学的診断、国としての施策、在宅医療や緩和ケア、新生児マススクリーニング、そして遺伝子治療を含む新しい治療法の開発など、先天代謝異常症を取り巻く幅広い分野の発表と議論が行われました。
多くの医師、研究者、看護師、コメディカルスタッフが参加し、職種を超えて互いに学び合い、高め合う場となりました。会場には活気があふれ、これまでの成果を共有しながら、次の時代の医療をどう築くかを真剣に考える姿が印象的でした。
窪田先生は、「100万人に一人の希少難病を持っているかもしれないけれど、目の前にお母さんに抱っこされて座っている一人の子どもとご家族のためにできるかを考え続けたい。」と語られ、医療者としての使命感と、患者・家族に寄り添う温かな思いが込められており、胸に深く響きました。

7.「閉会のあいさつ」
順天堂大学 難治性疾患診断・治療学 村山 圭 先生
村山先生からも参加者の皆さまへ熱いメッセージが送られました。チャットを通して、遺伝の専門用語や移植に関する質問が寄せられる中で、先生は「遺伝のことを正しく理解したうえで診療を進めていくことの大切さ」について丁寧にお話しされました。
また、コロナ禍以降、会場に足を運べなくても、ZoomやYouTubeなどを通じて情報を共有できることの大切さにも触れられました。医療や研究の話題を、遠くにいても皆で学び合い、つながれる場として、こうしたオンライン形式の重要性を改めて感じる時間となりました。
最後に村山先生からは、学会やフォーラムへのご感想、そして今後取り上げてほしいテーマなどをぜひお寄せくださいとの呼びかけがあり、温かい雰囲気の中でフォーラムは締めくくられました。

以上、2024年度先天代謝異常症患者会フォーラムが、盛況のうちに閉会しましたこと をご報告いたします。演者・座長の先生方、運営にご尽力いただいたフォーラム事務局の皆様、そしてご参加いただきました皆様へ、改めて御礼申し上げます。