

新生児マススクリーニングのパラダイムシフト
医誠会国際総合病院 難病医療推進センター 副センター長
酒井規夫
1.はじめに
新生児マススクリーニングはアメリカで1961年から,日本では1977年から始まった公衆衛生事業であり,治療法のある疾患で,早期診断・早期治療の意義のある疾患を対象として新生児のろ紙血を用いたスクリーニング法です。初期には食事療法で治療可能なアミノ酸代謝異常症などが対象でしたが,タンデムマス法という検査機器の発達で2014年からは日本では対象疾患も20種類ほどに増加し,2020年ごろからは重症複合型免疫不全症,脊髄性筋萎縮症,ライソゾーム病,副腎白質ジストロフィーなどが,治療法の開発もあって地域によっては対象疾患としてスクリーニングを始めるようになってきた経緯があります。
本稿では,対象疾患が増えてきたことにより,新たに出現してきた課題や,新たなスクリーニングの意義が出現してきており,この検査に対する考え方が変わってきており,新たなパラダイムシフトが来しつつあるという考えについてお話したいと思います。
2.対象疾患の選定
アメリカでは2008年にRUSP(Recommended Uniform Screening Panel)が策定され,新規疾患について新生児マススクリーニング対象疾患とすべきかどうかについて,一定の基準のもと点数評価を行い,その点数に応じて一番高得点のものは「core condition」その次の点数の疾患は「secondary condition」としてリストアップしています。またその評価は検査法や治療法の進歩とともに再評価を受けて,点数が上がればリストに載せるシステムです。現在日本で実証事業の対象になっているSCIDは2010年に脊髄性筋萎縮症(SMA)は2018年に追加となっており,その他の先天性代謝疾患としては2015年にポンペ病,2016年に副腎白質ジストロフィー(ALD),ムコ多糖症I型(MPSI),2022年にムコ多糖症II型(MPSII),2024年に乳児型クラッベ病がcore conditionとして追加されています。
一方日本においては,これらの疾患の検査は,有料検査として,地域により違う対象疾患に対して2020年ごろから増加してきている実態の中,SCID, SMAの2疾患に対して2024年からは実証事業としてこども家庭庁の施索として公費化のうえ自治体ごとに開始となっています。ライソゾーム病については,基本,有料検査としてパイロット的に検査実施をしており,最近いくつかの自治体では補助を始めたところもあるというのが実態です。また検査対象疾患はポンペ病,MPSI/IIの3疾患のみに実施しているところから最大10疾患を対象にスクリーニングをしているところもあり,現場の状況はかなりバラバラになっています。
3.先天性代謝疾患のパラダイムシフト
新生児マススクリーニングはフェニルケトン尿症のように,診断・治療しなければ重度の知的障害,てんかんなどを来すが,新生児期の診断,治療によりほぼ正常の生活ができるようになるという意味で,患者さん,患者家族にとり,また医療経済的にも大きな変化をもたらしました。これは新生児マススクリーニングの公衆衛生事業として,また小児医療における早期診断,早期治療ないし予防医療として疾患予後を大きく変えるものでした。
日本ではこれが始まって約半世紀となる今の時期において,先ほど述べたように対象疾患がさらに増える状況にあります。これは多くは先天性代謝異常症であり,遺伝性疾患であるために臨床的発症の前に生化学的に遺伝学的に診断することができるという特性を使うことにより可能にしたわけであります。
しかしながら,対象疾患が多様になる中で,今までは新生児マススクリーニングが「新生児期に診断・治療の意義が大きい疾患」に対して「新生児本人の診断・治療」を目指して行ってきましたが,これが少しずつ変わってきていることについて,コメントしたいと思います。
例えばファブリー病はX連鎖性疾患であり,古典型男児においても発汗障害,四肢の痛みなどの初期症状が出るのは4−5歳の幼児期であり,また治療介入も10歳前後からが望ましいとされています。つまり新生児期に診断しても,本人には何もすることはないが,母親やさらにその上の世代に治療を要する未診断のファブリー患者がいる可能性があり,新生児マススクリーニングで陽性者が出たことをきっかけとして,遺伝カウンセリングの上家系解析により複数人の患者さんの診断・治療が可能になると言えます。これは新生児マススクリーニングを受ける家族にとっては晴天の霹靂と感じる可能性があり,検査の前に十分な説明がなされるべきであると,「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン2022」にも記載されています。また本疾患はX連鎖性疾患ではありますが,女性でも発症することが多く,検査も酵素活性で行うために女児でも陽性になる可能性があり,同様に両親やその上の世代に罹患者の診断につながる可能性がありますが,本人の治療開始が男児よりさらに遅くて良いこと,女児は酵素では見落とすことがあることなどにより,新生児マススクリーニングの対象に女児を入れない地域もあります。
また副腎白質ジストロフィーもX連鎖性遺伝疾患であり,大脳型で発症すると非常に急速に発症し,ごく初期に実施する造血幹細胞移植のみが唯一の治療法ですが,実施できない場合には短期間に寝たきりの状態になってしまう疾患です。また発症時期は今までの報告では2歳が最も早い時期ですので,その頃から頭部MRIで早期発症をフォローすることにより,臨床的な発症前で画像での発症初期に造血幹細胞移植の実施により,最善の治療効果が期待できるようになります。ただ,この疾患の困難なところは病的バリアントを持っていて,同じ家系内で発症している人がいても,発症時期も同じではないし, 2歳以降長期的な画像フォローが必要となることもあり,発症を予想できるようなバイオマーカーの発見が望まれます。この疾患においても,本人以外に保因者女性の検索や,未発症患者さんの診断,フォローの可能性が出てくるため,その家族のためのマススクリーニングでもあると考えられます。
また,現在は新生児マススクリーニングは遺伝学的検査であり,特に発症前診断にもあたるという意味で,十分な検査前の説明とインフォームドコンセントの上に実施するのが望ましいと言えます.
つまり,1977年から行ってきた「新生児マススクリーニング」は,新生児のためだけのものではなくなりつつあり,公衆衛生事業としての「マス」で実施すという概念から,家族の同意のもと進めていくべき検査として「新生児期遺伝性疾患検診」とでも呼ぶべき検査として,すでに進みつつあるということを,医療者も,一般の方も,十分認識すべきであると考えています。そしてこの状況を社会に広めていくことにより,日本で生まれるすべての新生児にとり,またその家族にとって意義のある検診として平等に選択することができるようにすることが,我々先天代謝異常症を専門にしているものの使命と考えます。
4.クラッベ病の新世紀
この拡大新生児マススクリーニングの中でも,クラッベ病は独自の歴史と特性を持っているといえます。クラッベ病は異染性白質ジストロフィー,副腎白質ジストロフィーと並んで代謝性白質ジストロフィーとして,小児期発症の進行性脱髄疾患として重要な疾患といえます。また,クラッベ病の病型はその発症時期,重症度により乳児型,後期乳児型,若年型,成人型と非常に幅の広い臨床スペクトラムを持つ疾患です。そして早期の造血幹細胞移植の有効性の知られている代謝疾患としても代表的なものです。ただ,造血幹細胞移植については,発症が1歳未満の乳児型については,未発症時期である生後30−45日以内という超早期に実施することが条件であり,これより遅くなってはその効果は不十分というか,かえって疾患の進行を早めるのみとなることが報告されています。また発症が1歳以降の遅発型の移植については,症例報告はあるがその移植時期や有効性についてのエビデンスが少ないと考えられています。
このような状況の疾患に対して,アメリカ,ニューヨーク州では2006年から新生児マススクリーニングが開始されていますが,これには乳児型クラッベ病のお父さんでスポーツマンであるハンターさんの働きかけ(HP: Hunter’s hope)が大きいのではと思います。しかしながらクラッベ病は90%が乳児型と教科書にも書かれていましたが,実はそんなに多くないこと,酵素活性は低値でクラッベ病と疑われるが,遺伝子型で乳児型が確認できないため移植せずにフォローとなる方が結構多いことなどもあり,クラッベ病は新生児マススクリーニングをすべきかどうかという議論があり,論文上でも多くの議論を重ねてきました。そのような中,新生児マススクリーニング用のろ紙血でのバイオマーカーであるサイコシンの定量により遺伝子型ではなく乳児型の診断ができるという研究が進み,2024年2月になりRUSPにおいて,一次検査にて酵素活性を,それて疾患が疑われれば二次試験としてサイコシンを定量し,10nMというカットオフ値を設定するとことにより,乳児型クラッベの診断が可能ということで,2024年2月に提出されたRUSPの審議により「乳児型クラッベ病」が,core conditionに追加されることになり,現在アメリカでは12州において対象疾患として選ばれています。
日本では最近までクラッベ病は新生児マススクリーニングの対象疾患として選ばれていませんでしたので,乳児型クラッベ病の患者さんは,乳児期に症状が出てから診断されることになりますので,診断時にはすでに造血幹細胞移植の治療選択はあり得ませんでした。今まで兄弟が乳児型クラッベ病と診断されたために,次子として生後すぐに診断し,造血細胞移植のチャンスがあった患者さんは今までたった3人です。そのうちお一人はずいぶん以前の症例ではありますが,移植後の合併症で亡くなられました。後の2人は無事生着し,ご兄弟の経過とは明らかに改善した経過を示しています。アメリカの移植を受けた症例においても,末梢神経障害による歩行障害などは残存しますが,中枢神経症状の進行は抑えられて明らかな効果があることが報告されています。
大阪市では2024年4月から,長野県などでは2025年4月からクラッベ病の新生児マススクリーニングが始まったことにより,疾患の兄弟がいない家庭において生まれた乳児型クラッベ病の赤ちゃんは,生後30−45日という早期の時期に造血幹細胞移植を受けるチャンスが出てきたということになります。20万人に1人,その中の4割前後の赤ちゃんが乳児型と考えられますので,そんなに多い数ではないですが,
これからはこの検査により,造血幹細胞移植という,リスクはありますが保険で認められた有効性のある治療を選択することができるようになったと言えます。クラッベ病の患者さんにとって,新たな時代を迎えたと言えるのではないでしょうか. 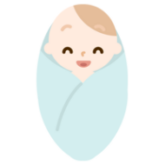
全文PDFは以下よりダウンロードできます。